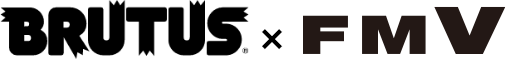- 塚本由晴(左)
- つかもと・よしはる/1965年生まれ。建築家。1992年、貝島桃代と〈アトリエ・ワン〉を設立。2000年東京工業大学大学院博士課程修了、博士(工学)。東京工業大学大学院教授。ハーバードGSD、UCLA、コロンビアGSAP、コーネル大、ライス大、デンマーク王立芸術アカデミー、ETHZなどで客員教授を歴任。
- 速水健朗(右)
- はやみず・けんろう/1973年生まれ。ジャーナリスト。食や政治、都市、ジャニーズなど複数のジャンルを横断し、ラジオやテレビにも出演。〈団地団〉としても活動中。近著『東京どこに住む 住所格差と人生格差』(朝日新書)、『東京β』(筑摩書房)など。TOKYO FM『TOKYO SLOW NEWS』パーソナリティも務める。