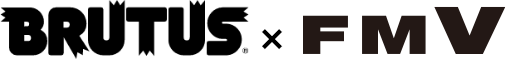官僚が会議の文書を残さない、みたいなことが今の日本では繰り返し問題になります。何かを残すということは、高山さんが小説家になる前にいた美術の世界の関心事でもありますよね。
レオナルド・ダ・ヴィンチくらいの昔だと、医学と建築と美術などの知識に現在のような境界はなく、博物学的な考えかたが強かったんだと思います。コレクションは人に見せるためであると同時に、貴族やエスタブリッシュメント層がまず所有するためのものだったりして。
作品を残すことと、技術そのものを残すことの意味が重なっていた時代。しかも残すのは王族とか貴族といった有力者が個人的にコレクションしていたものだったということですね。
日本も景気が良かったころは、地方のお金持ちがパッションで集めたコレクションをミュージアムとして全国のあちこちで公開していたりという文化がたくさんありましたよね。いまでも名残りがあります。ブンダーカンマーの”驚異の部屋“じゃないですけど。
麻雀博物館が千葉の外房の海の近くにかつてあったり、箱根に謎の博物館がたくさんあったりしましたよね。多分、急速に減ってますが。
景気が良いと、郷土の資料を集めているような趣味の研究のような行為が、アカデミズムではない場所にまで広がっていく。大衆知が堆積していくことは、そういうあらゆることのアーカイブにも顕れるのではないかなと。
『首里の馬』の主人公が勤めている小さな郷土資料館って、誰も意味を見出していない郷土的資料が集っている場所という設定ですが、イメージの中に地方のミュージアムも入っている?
そういうところもあると思います。全国のロードサイドにある謎のミュージアムと郷土資料館的な断片の集積される場所が気になっていたりそういう、小さな疑問が積み重なって、断片が合わさって一本の小説になっていったところがあります。
『暗闇にレンズ』だと、明治期にどう映画が輸入されてきて、広まったかみたいなことをすごく掘り下げて調べたりしてますよね。資料魔的なところがあるのかなと思ったんですが。
基本的にはフィクションは”ほら話”でもあるんです。資料を使っていようが、それをどうほらの材料にしてやろうというところで物語を作ります。でも、ほらを書く以上、倫理を大事にしたいという思いもあります。例えば、『首里の馬』の主人公は盗みもする。かなり危うい人物だと書いた人間でさえ思います。それを読んでいる人はどう受け止めるだろう、例えば、違う文化の地域からはどう見えるかなとか、そういうことは常に頭に置いて書いています。
『首里の馬』の舞台は沖縄ですけど、その理由ってあったんですか?
実際に現地に行って見たものの蓄積なんですが、例えば、首里城も昔からお城があったわけではなくて、戦後に再建されるときに、学術的な研究や建築の技術だけでなく、大衆文化に残された建築の技術や文化が組み合わさっているんです。そして、再建費用の一部に、アメリカ資本が混ざっているような部分もある。私はそういうモザイク状にいろいろな要素が絡み合っている話が好きなんです。
わかります。沖縄の町もモザイク状に過去や文化が集積していますよね。琉球古来の文化とアメリカ占領時代の混ざり方が独特ですし。
言ってみれば”歴史のジグザグ感”のようなものですよね。それって”知の保存”にもつながってくる話です。物事って全部がきちんと積み上がるわけではなく、ジェンガじゃないけど、抜けているものもある。そして、その抜けを支えているものもある。
そういうモザイクのかけらを集めて小説にしていく手法は、おもしろいですね。歴史を振り返るときに漏れ落ちるものって、近々の過去であってもたくさんあります。
私が大学を卒業する頃なので、20年以上前ですが、インターネットを始めたときに自分のホームページを置いておけるジオシティーズというサービスがあったんですよ。
僕もジオシティーズでホームページ持ってました。ブログが出てくる前の時代、90年代末から2000年代初頭が全盛期ですかね。
掲示板とかでキリ番がなんとかとか言っていたはず。でもそれは、サービスが終了して、ある日すべてのデータが消去されたんですね。当時、あの場所を利用していた女子や男子の気持ちとか知も雲散霧消しているんだろうなって。
デジタルデータなんだから物質でもないわけで、残せばいいのにと思いますが、案外残らないですよね。コストなんてたかが知れてると思うんですが、それを残すことの重要性って議論になると、”いらないかも”ってなりますよね。地方のヘンテコミュージアムもそうですけど、公式の官の記録やデジタルメディアですらなくなる時代です。その中で何を残したり、見つけ出したりするか。現代版の民俗学のようなものが必要な気がします。
二冊目の拙著『オブジェクタム』という作品を制作しようとしていたころは、赤瀬川原平さんが亡くなったときなんですね。赤瀬川さんの思考の仕方とか、回り込んでものを見たりっていうことに影響された部分は大きいんです。
そもそも美術家であり小説家であるという赤瀬川さんと立ち位置も似てますね。
私は日本画で、赤瀬川さんは現代美術家という違いはありますけど、影響された部分はとても多いと勝手に思っています。いっぽうで、『首里の馬』は、今和次郎さんの提唱された”考現学” なんかについても考えながら書いた部分はあります。考現学は「現在のことを考える」学問なわけですが。今だったら、どうでしょう、駄菓子屋さんにどういうお菓子があって、一番安いのは5円のチョコ、とかそういうのに近い”知のあり方”をずっと考えていたんです。
考現学から路上観察学へという流れが『首里の馬』につながっていてと考えると、いろいろ腑に落ちる部分があります。ちょっと昔のクイズ番組が、社会でどんな意味を持っていたのかという発想もまさにそうですよね。ちなみに赤瀬川さんといえば千円札の表面を印刷、加工した作品に対する「千円札裁判」も忘れてはいけません。
変な話、偽札っておもしろいんです。お札って物語としていろんなことが書いてあるし、テキスト情報であり、印刷技術でもあるし、たくさんの人が持っている絵画、つまり複製芸術でもある。日本の偽札史を遡ると、「チ-37号事件」という事件があるんですよ。1961年、秋田で聖徳太子の千円札に、それはもうそっくりなスーパー偽千円札が見つかって、懸賞金までかけられたんですが、未解決のまま時効を迎えたという事件です。興味深いのは、偽造したのが千円札だったところで、儲けることがきっとそこまで強い目的じゃなかったんじゃないかって思っていて。
効率だけを考えるのであれば、当然、高額紙幣を偽造しますよね。一万円札を刷ったほうがコスパがいい。
そもそも捕まったときの刑罰も重いので、同じリスクであれば一万円札を刷りますよね。だから、名誉欲みたいなものなのかもしれないですよね。偽札って、社会経済のシステムそのものへのテロリズムで、混乱が目的だったのかという気もします。
偽札といえば、アイザック・ニュートンって、造幣局長として偽造通貨の有能な取締捜査官だったという話もありますね。印刷は科学の先端だったので、化学の知識が必要だったと。あとヒトラーは、戦争末期に偽ポンドの印刷工場をつくってイギリスに対抗しようとした話もあります。
偽札づくりって兵器のように誰かを直接殺したり傷つけるのではなく、システム自体を麻痺させる手段なんですよね。ほかにも例えば映画もそうで、第二次世界大戦でも戦争の手段として映画が使われました。ディズニーのキャラクターが出てきて、戦争を啓蒙するプロパガンダに使われたりというのもそうですね。
芸術はそれ自体でお腹いっぱいにはならないけど、それはそれでいろいろに利用されたりしていて。
小説も時代を超えて人に影響を与えることのできる武器なのかなと思いますが、今の時代のヒントを考える上で、小説家という職業について思うところってありますか。
小説家は、今起こっていることを書いて知らせるというよりは、タイムラグがあって、時間を置いてから何かを書くという職業なんではないかと考えています。例えば、最近は好きな野球についての原稿を頼まれることがあるんですけど、プロのスポーツの記者の人たちは、その試合のことをすぐに伝えなくてはならない。その力は私にはない。試合後どころか、シーズン後になってしまう。でも、すぐに反応することとは、違うものを残す側面があるんだと思います。物事は、すぐに答えを出せばいいものではなくて、熟成が意味を持つことがあるんじゃないかって。