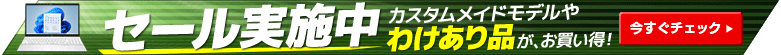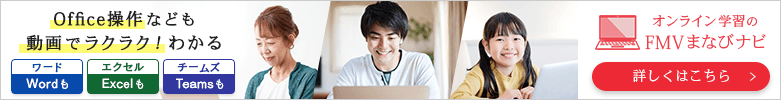パソコンに、料金を請求する画面が表示され続けて消せなくなってしまったり、パソコンを起動するたびに広告などが表示されたりするときは、悪意のあるプログラムがインストールされている可能性があります。
その場合の対処方法は、次のQ&Aをご覧ください。 故障やウイルス感染、外国語、アダルト向けなど、意図しないページやお知らせが表示されます。
故障やウイルス感染、外国語、アダルト向けなど、意図しないページやお知らせが表示されます。
Q&Aナンバー【3505-5975】更新日:2019年4月13日
このページをブックマークする(ログイン中のみ利用可)
メールやホームページのリンクをクリックしただけで、画面に「有料会員登録しました」や「請求書」などと表示され料金を請求されました。
| 対象機種 | すべて |
|---|---|
| 対象OS |
|
 質問
質問
IPアドレスやホスト名が表示され、料金を請求されました。
どのように対処すればよいのかを教えてください。
 回答
回答
利用料金や利用規約に対する十分な説明がなく、メールやホームページに記載されていたアドレスや画像などクリックしただけで、自動的に有料会員登録をしたように見せかけ、料金を請求する詐欺が増加しています。
これらは「ワンクリック詐欺」と呼ばれる不当請求です。
ワンクリック詐欺について詳しくは、次の項目を確認してください。
ワンクリック詐欺の特徴
ワンクリック詐欺には、主に次のような特徴があります。
- メールやホームページのリンクをクリックするだけで、「請求書」「会員登録を完了した」「入会ありがとうございます」などが表示されます。
メールでの請求の場合、差出人が詐称され、プロバイダなどから送信された広告メールに見えることがあります。 - 請求についての説明の中で、法律の名前や、裁判所、弁護士などの言葉が使われ、正式な請求であるかのように見せかけられています。
また、入金がない場合、回収業者が自宅などに直接訪問して回収するなどと表示されることもあります - 「IPアドレス」「プロバイダ名」「メールアドレス」「ホスト名」「固有識別コード」「ご利用のOS」などが画面に表示され、個人情報を把握しているように見せかけます。
インターネットでは、「IPアドレス」や「ホスト名」などは、ホームページを表示するだけで必ず相手に伝わる仕組みになっています。これらの情報がわかっても、名前・住所・電話番号などの個人情報が業者に伝わることはありません。
また、これらの情報を元にして業者がプロバイダに個人情報の開示を要求しても、プロバイダが応じることは通常ありません。 - 「退会手続きをしない場合は料金が発生します」などと、退会手続きのための連絡先などが記載されていることがあります。
この連絡先には問い合わせをしないようにしてください。問い合わせをした結果、電話番号や住所、氏名などの個人情報を与えてしまい、悪用されてしまう可能性があります。
ワンクリック詐欺の他に、信頼性のある会社などになりすまし、クレジットカード番号や暗証番号といった個人情報を盗みとる「フィッシング詐欺」も被害が増えてきています。
「フィッシング詐欺」についての詳細は、次のQ&Aをご覧ください。 フィッシング詐欺について教えてください。
フィッシング詐欺について教えてください。
請求された場合の対処
ホームページやメールで料金を請求された場合は、次のように対処します。
次の項目を順にご覧ください。
送信元には問い合わせない
料金を請求するという画面表示やメールの督促があっても、送信元に問い合わせたりメールを返信したりしないようにします。
メールの連絡・返信、電話での問い合わせなどを行うと、それによって個人情報が特定されてしまいます。
登録の解除方法・退会手続きなどが画面に出ていても、アクセスしないようにします。手続きをすることで、新たな個人情報を相手に知らせることになります。
不当請求に対しては、一切無視してかまいませんが、裁判所からの書類を無視した場合は不利益をこうむる恐れがあります。裁判所からの書類(と称している書類)が送付されてきた場合は、書類に記載されている連絡先には連絡をせずに、最寄の消費生活センター(国民生活センター)に相談してください。
国民生活センター
全国の消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
請求内容を確認し契約が有効かどうかを判断する
請求された料金をあわてて支払ったりせずに、請求内容をよく確認して契約が有効かどうかを冷静に判断してください。
「登録されました」「契約が成立しました」などと表示されていても、契約が有効であるとは限りません。
事業者側は消費者に対して契約が成立する前に、利用規約や料金等をわかりやすく明示し、その同意を求める必要があります。
利用規約などが表示されていた場合でも、料金がいくらかかるかが容易に判別できなかったり、最終的に「申し込み」ボタンなどを押す前に申し込み内容を再確認する画面が表示されていない場合などは、契約の錯誤無効を主張できる可能性があります。
電子商取引については、次の経済産業省のホームページの「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」にわかりやすく記載されています。
経済産業省
電子商取引(EC)の促進
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/index.html
判断がつかない場合は公的機関に相談する
契約が有効であるかどうか判断できない場合は、最寄の消費生活センター(国民生活センター)へ相談してください。
国民生活センター
全国の消費生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
請求に応じて金銭を支払ってしまったり悪質な請求が繰り返されたりする場合など、実際に被害を受けた場合は、都道府県警察サイバー犯罪相談窓口や最寄の警察署に相談してください。
警察庁
都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧
http://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
被害にあわないための予防策
被害にあわないためには、次のように心がけます。
- 覚えのない広告メールや信頼できないホームページのリンクは不用意にクリックしないようにします。
- 料金や解約方法が明記されている利用規約が、わかりやすい場所に書いてあるか確認します。
「入口」「こちらをクリック」などをクリックしてしまう前に、利用規約を確認するようにします。 - メールアドレスが書いてあっても不審なメールには返信をしないようにします。
また、メール配信の解除方法などのリンクが記載されていても、アクセスしないようにします。返信や解除手続きをすることで、メールアドレスが有効であることが相手に把握されてしまいます。
次の公的機関のホームページも参考にしてください。
国民生活センター
あわてないで!! クリックしただけで、いきなり料金請求する手口
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/click.html